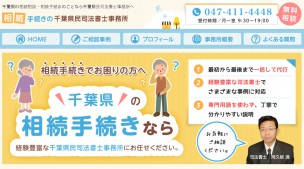住宅ローンを残して亡くなってしまった場合
住宅ローンは長期間に渡る契約内容になっていますので,その返済途中で,住宅ローンを借りた方が亡くなることもしばしばあります。
住宅ローンには,基本的に,住宅ローンを借りた方に生命保険(団体信用生命保険)を住宅ローンと共に契約しており,住宅ローンを組んでいる方の約95%が加入しています。
この保険は,住宅ローンを借りた方が死亡や高度障害になり住宅ローンの支払いができなくなった場合に備えた保険で,死亡当時の住宅ローンの残債全額が保険金で支払われるものです。
この保険金によって,住宅ローンは完済となりますので,以後,住宅ローンを相続人が支払う必要もありませんし,不動産も,相続人の方が負債のない不動産として相続することができます。
相続人が,保険の存在を知らず,住宅ローンの返済を継続していた場合
住宅ローンを借りた方が死亡した後に,住宅ローンの返済は銀行口座からの引落しがほとんどですので,預金残高があり,銀行に届け出なければ,毎月引落しが実行されます。
上記保険に加入していたことを知らない相続人の方で,銀行に死亡届をせず,そのままにして,住宅ローンの返済が継続していた場合はどうなるのでしょうか?
この場合は,団体信用生命保険契約においては,住宅ローンを借りた方が亡くなった時点で保険金が支払われることになっているので,本来であれば,支払う必要のないものを支払い続けたことになる結果,死亡後に支払ったものの返還を受けることができます。
しかし,住宅ローン債権者は(銀行等)は,相続人から情報を提供しない限り,詳しい状況が分かりませんので,事情を説明する必要があります。
住宅ローンに関する抵当権抹消の手続き
団体信用生命保険金で,住宅ローンの残債がなくなると,次に行うのは,不動産に設定された抵当権の抹消手続きです。
保険金で住宅ローンが完済になっても,金融機関(銀行等)は,自動的に抵当権の抹消手続きを行ってくれることはありません。
まず,住宅ローン債権者から住宅ローンの金銭消費貸借契約書や抵当権設定契約証書など,抵当権を抹消するための書類を送ってくるか,または銀行に受け取りにくるようなご案内があります。
金融機関(銀行等)がやってくれるのはここまでです。
抵当権抹消に必要な書類を受領した相続人の方は,ご自身で管轄法務局に行って抵当権抹消の手続きをするか,あるいは司法書士に抵当権抹消の手続きを依頼することになります(銀行等から受領した書類の中に,このような案内もあります。)。
抵当権の抹消登記には,登録免許税を支払う必要があり,登録免許税の額は,不動産1つあたり1000円となります(土地1筆と建物1棟であれば2000円)。
なお,同一管轄の法務局で20物件を超える場合には,申請1件あたり2万円が上限となります。
銀行等から書類が送られてきたら,できるだけ早い段階で,抵当権抹消の手続きされた方がよろしいかと思います。
たまに見かけますが,銀行から受領した抵当権抹消書類を何年間も放置した結果,書類の紛失や,抵当権者の合併,あるいは,次の相続が発生するなどして,書類を受領した段階で抵当権抹消登記申請をしていれば,比較的簡単に終えることができた手続きが,大変複雑になってきてしまいます。
ここで大きな注意点ですが,上記の抵当権抹消登記申請の前に,相続による不動産の所有権移転登記を行わなければならないということになります。
つまり,当該不動産の所有権を相続人に移転し,その後に,抵当権の抹消登記申請をする,ということになります。
なぜかというと,時系列的に,住宅ローンを借りていた方が死亡し,それにより保険金が支払われて住宅ローンが完済となったため,抵当権を抹消できるのは,不動産を所有した相続人からの申請に基づいて行われるため,その前提として,所有を相続人として所有者の移転手続きを前提として行わなければならないのです。
抵当権抹消登記申請の前に,所有権者を,住宅ローンを借りていた方から相続人に変更しなければ,物権変動の過程を忠実に反映させるというという不動産登記法上の要請にも応えられないため,このような流れになるのです。
似て非なるものとして,相続が発生する前(住宅ローンを借りた方が死亡する前)に,住宅ローンを完済した場合(住宅ローンを組んだ方が繰り上げ返済や約定返済によって完済)には,物件変動の順番としては,住宅ローンの完済の後に死亡と続くため,所有者(権)の移転登記を行うことなく,抵当権の抹消登記申請を,相続人が行えることになります(その後に相続による所有権移転をしても問題なし)。
簡単に区分すると,住宅ローンを完済したとき(抵当権抹消原因が発生したとき)に,住宅ローンを借りた方が生きていたのか,あるいは亡くなっていたのかで区別すると理解しやすいと思います。
団体信用生命保険と相続税
通常の生命保険ですと,保険金が相続人に支払われた場合,みなし相続財産となりますが,団体信用生命保険は,相続人には支払われる性質のものではありません。
したがって,通常の生命保険とは異なり,みなし相続財産には該当しません。
また,相続税で,債務控除というものがありますが,住宅ローンの残債は,相続開始時において確実な債務ということができず,住宅ローンの残債は,死亡と同時に保険金によって完済となるため,これを債務控除することはできません。
以上の結果から,
①団体信用生命保険金は,相続財産に加えない。
②住宅ローンの残債は,債務控除しない(できない)。
③住宅ローンの抵当権が設定された不動産を負債のない不動産として評価する。
ということになります。
それでは,団体信用生命保険に入っていなかった場合はどうでしょう?
相続人の方は,住宅ローンの残債(負債)を法定相続分の割合に従って引き継ぐことになります。
住宅ローンを借りた先(銀行等)には,相続の届出と,今後,誰が住宅ローンを支払っていくのか,所定の書面の提出を依頼されます。
債務も遺産分割の対象とすることができますが,債務については,対債権者の関係もあることから,この債権者(住宅ローン債権者)の同意なく,引き継ぐ債務の割合を相続人間で勝手に遺産分割協議で決めたとしても,相続人間では有効であるものの,住宅ローン債権者に対しては,遺産分割で決めた法定相続分とは異なる割合を対抗することができません。
これは,遺産分割協議によって,資力のない相続人に集中させることも考えられるところ,このような自由があると,債権者に不当な不利益を課してしまうことになるからです。
そのため,銀行等に対し,ある特定の相続人が引き継ぐものと届け出たとしても,その特定の相続人が住宅ローンの支払いをストップするようなことがあれば,他の相続人に対し,相続分に応じて請求していくことになるでしょう。
このような不安定な立場を解消する方法として,免責的債務引受といって,特定の相続人が,他の相続人の債務も全て引継ぎ,引継ぎをした他の相続人は,住宅ローン債務から逃れることができます。
しかし,これは,銀行等の同意が必要でありますし,かつ,特定の相続人(引き継ぐ人)の審査(住宅ローンを借り入れる際に行う審査同様)を行い,その審査をクリアーしてはじめて,他の相続人は相続した住宅ローン債務から離脱できるのです。
または,住宅ローン債務を引き継ぎたくない相続人の方は,相続放棄をすることもできます。
相続放棄の申述が家庭裁判所で受理されれば,住宅ローンの支払い義務は原則なくなりますが,相続登記をして名義人となったり,亡くなられた方の預貯金を取り崩して自己のために費消したりするなどした場合は,単純承認したものとみなされ,相続放棄の申述が受理されない場合もあり得ますので,相続放棄をするかどうか迷ったら,亡くなられた方の遺産には一切関わらない(手を付けない)ことが賢明です。