1 遺言書の検索 多く利用されているのは,「自筆証書遺言」「公正証書遺言」ですので,公正証書遺言については,お近くの公証役場で公正証書遺言の検索をすることもできます。必要書類がありますので,まずはお近くの公証役場で確認をし,予約を入れてみてください。 自筆証書遺言については,ご自宅に保管されているか,専門家を介していると,その専門家の方に預けているケースもあります。 2 相続人の確定 戸籍謄本,除籍謄本,原戸籍謄本で確認できますが,外国人の方については戸籍制度がない国が多いため,出生証明書等を本国官憲で発行してもらうことも必要になります。 3 相続財産の確定 遺産分割や相続放棄等の検討のため,相続財産の把握が重要です。 相続財産は早めに確認しておいてください。 4 相続放棄申述 相続人になったことを知ってから3か月間という短い時間が設定されていますので,相続の放棄をする方は,お亡くなりになられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを行う必要があります。 5 準確定申告 これまで確定申告をしていた方が亡くなった場合,死亡後4か月以内に確定申告をしなければなりません。 こちらも短い期間が設定されていますので,お亡くなった方がどのような仕事をしていたのか把握していないといけません。 6 遺産分割 相続人全員で,どの遺産を誰が相続するのか決める必要があります。 それを書面化したのが,遺産分割協議書です。 7 相続税の申告 基礎控除額を超える場合,10か月以内に相続税の申告をする必要があります。
相続
自筆証書遺言について
改正の趣旨 改正法による改正前の民法においては,自筆証書遺言は,全文,日付及び氏名を全て自書し,これに押印をしなければならないとされていたが,この負担を軽減して自筆証書遺言の利用を促進する観点から,その一部が緩和されるものである。改正の概要 自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には,その目録については,自書することを要しないとされ,この場合において,遺言者は,その目録の毎葉に署名し,印を押さなければならないこととされた。これにより,遺言書の末尾に添付されることが多いいわゆる遺産目録については,各ページに署名し,印を押したものであれば,パソコン等により作成したもの,遺言者以外の者が代筆したもの,登記事項証明書等を添付してこれを目録とするもの等であっても認められることとなる。なお,この目録中の加除その他の変更については,この目録以外の部分と同様に,遺言者が,その場所を指定し,これを変更した旨を付記して特にこれに署名し,かつ,その変更の場所に印を押さなければ,その効力を生じないとされた。おって,平成31年1月13日前にされた自筆証書遺言については,なお従前の例によることとされた(改正法附則第6条)。これにより,平成31年1月13日より前に作成された自筆証書遺言については,相続開始が同日以降であっても,従前どおり,全文,日付及び氏名が全て自書されていない場合には無効となるので,留意する必要がある。
相続の基本3類型
相続する前に知っておきたい3形態(相続の種類)
①単純承認
相続が発生すると,被相続人が一身専属している権利と義務以外の全ての権利と義務が相続人に承継することになります。
権利も義務もということなので,土地の所有権も預貯金債権も被相続人の借金もその全てが承継されます。
相続が開始して,最も多い形態が,この単純承認です。
民法921条では,次に掲げる場合には,相続人は,単純承認したものとみなすとして,
1 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸借をすることは,この限りでない。
2 相続人が第915条第1項の期間内(相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に,相続について,単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。)に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
3 相続人が,限定承認又は相続の放棄をした後であっても,相続財産の全部若しくは一部を隠匿し,私にこれを消費し,又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなったとき。
と定められており,3か月という短い熟慮期間内(期間伸長は申立てにより可能)にどの相続形態を選択するかを決めなければならず,その期間を徒過することによって,単純承認していることも多いと思われます。
相続の限定承認や相続の放棄と異なり,単純承認は,家庭裁判所の手続きを経ることなく,最もオーソドックスなスタイルといえますが,消極財産(マイナス財産)が積極財産(プラス財産)より多かったとしても,その負の遺産も相続人が承継することになります。
また,3か月が経過しなくても,相続人が相続財産の一部でも処分したときは,単純承認したものとみなされてしまうため,プラス財産が多いのか,あるいはマイナス財産の方が多いのか確定しない段階においては,被相続人の財産に一切手を付けないことが重要になってきます。
例えば,相続登記をしてしまった後に,莫大な負債が見つかっても,「今から相続の放棄をしよう」としても,単純承認をしたとみなされる結果,もはや相続の放棄をすることはできず,被相続人の借金を返していくか,あるいは相続人自身で支払いが困難であれば自己破産等の債務整理を行う必要も出てきます。
なお,民法915条第2項では,「相続人は,相続の承認又は放棄をする前に,相続財産を調査することができる。」との規定があるため,相続形態を選択する前に遺産の調査を行うことができますが,実際には,三か月以内では足りない場合も多々あるため,この場合には,家庭裁判所に対して,期間伸長の申立てをして,その審判を得てさらに遺産の調査を続行することになります。
職権消除と相続財産管理人選任の申立て
市長村長が,職権消除した者について,相続が開始したことになるのか?
「事案の概要」
① 所在不明者が100歳以上の高齢に達している場合には,市町村長が職権により死亡記載をすることができる(戸籍法44条3項・24条2項),というのが戦前からの戸籍実務の取扱いである(高齢者職権消除。大正5年2月3日民事第1836号司法省民事局長回答,昭和6年2月12日民事第1370号司法省民事局長回答,昭和24年9月17日民事甲第2095号法務省民事局長回答,昭和32年1月31日民事甲第163号民事局長回答「100歳以上の高齢者の所在が不明で,その生死及び所在につき調査の資料を得ることができないときは,市町村長より職権消除の許可申請書にその事由を記載し戸籍謄本及び戸籍附票謄本を添付させ,監督法務局又は地方法務局の長においてその消除を許可して差し支えない。」)
②高齢者職権消除の手続きにより,A女の戸籍は,昭和27年11月6日付け許可を得て,同月10日に除籍された。
③そこで,Xは,Aの除籍謄本を添付して,松山家庭裁判所に,相続財産管理人の選任の審判申立てを行った。
遺言内容と異なる遺産分割協議
相続で,よく相談を受ける一つのテーマとして,
遺言内容と異なる遺産分割協議はできるのでしょうか?
前提条件として,
① 遺言で,遺産分割が禁止されていない。
② 遺言執行者が定められていない(厳密にいうと,遺言執行者が同意すれば可能)。
③ 相続人全員の合意がある。
以上を満たしている場合,次の裁判例によっても,認められています(上記②には裁判例がありますが,割愛してます)。
[さいたま地方裁判所平成14年2月7日判決]
(1)特定の不動産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言がなされた場合には,当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなど の特段の事情のない限り,何らの行為を要せずして,被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに当該不動産は当該相続人に相続により承継される。そのような遺言がなされた場合の遺産分割の協議又は審判においては,当該遺産の承継を参酌して残余の遺産の分割がされることはいうまでもないとしても,当該遺産については, 上記の協議又は審判を経る余地はない。以上が判例の趣旨である(最判平成3年4月19日第2小法廷判決・民集45巻4号477頁参照)。
しかしながら,このような遺言をする被相続人(遺言者)の通常の意思は,相続をめぐって相続人間に無用な紛争が生ずることを避けることにあるから,これと異なる内容の遺産分割が全相続人によって協議されたとしても,直ちに被相続人の意思に反するとはいえない。
被相続人が遺言でこれと異なる遺産分割を禁じている等の事情があれば格別,そうでなければ, 被相続人による拘束を全相続人にまで及ぼす必要はなく,むしろ全相続人の意思が一致するなら,遺産を承継する当事者たる相続人間の意思を尊重することが妥当である。 法的には,一旦は遺言内容に沿った遺産の帰属が決まるものではあるが,このような遺産分割は,相続人間における当該遺産の贈与や交換を含む混合契約と解することが 可能であるし,その効果についても通常の遺産分割と同様の取り扱いを認めることが実態に即して簡明である。また従前から遺言があっても,全相続人によってこれと異なる遺産分割協議は実際に多く行われていたのであり,ただ事案によって遺産分割協議が難航している実状もあることから,前記判例は,その迅速で妥当な紛争解決を図るという趣旨から,これを不要としたのであって,相続人間において,遺言と異なる遺産分割をすることが一切できず,その遺産分割を無効とする趣旨まで包含していると解することはできないというべきである。
(2)本件においては,本件土地を含むDの遺産につき,原告ら全ての相続人間において,本件遺言と異なる分割協議がなされたものであるところ,Dが遺言に反する遺産分割を禁じている等の特段の事情を認めうる証拠はなく,原告らの中に本件遺産分割に異議を述べる者はいない上,被告は本件遺産分割については,第3者の地位にあり,その効力が直ちに被告の法的地位を決定するものでもないことを考慮すると,本件遺産分割の効力を否定することはできず,本件土地は原告らの共有に属すると認められる。
国税庁のホームページより ,
遺言書の内容と異なる遺産の分割と贈与税
【照会要旨】 被相続人甲は,全遺産を丙(三男)に与える旨(包括遺贈)の公正証書による遺言書を残していましたが,相続人全員で遺言書の内容と異なる遺産の分割協議を行い,その遺産は,乙(甲の妻)が1/2,丙が1/2それぞれ取得しました。この場合,贈与税の課税関係は生じないものと解してよろしいですか。
【回答要旨】 相続人全員の協議で遺言書の内容と異なる遺産の分割をしたということは(仮に放棄の手続きがされていなくても),包括受遺者である丙が包括遺贈を事実上放棄し(この場合,丙は相続人としての権利・義務は有していま。),共同相続人間で遺産分割が行われたとみて差し支えありません。したがって,照会の場合には,原則として贈与税の課税は生じないことになります。
千葉県での相続なら,
http://chibakensozoku.jp/
当事務所オフィシャルHP(千葉県民司法書士事務所)
http://chiba-shihoshoshi.com/
住宅ローンを残して亡くなってしまった場合の相続
住宅ローンを残して亡くなってしまった場合
住宅ローンは長期間に渡る契約内容になっていますので,その返済途中で,住宅ローンを借りた方が亡くなることもしばしばあります。
住宅ローンには,基本的に,住宅ローンを借りた方に生命保険(団体信用生命保険)を住宅ローンと共に契約しており,住宅ローンを組んでいる方の約95%が加入しています。
この保険は,住宅ローンを借りた方が死亡や高度障害になり住宅ローンの支払いができなくなった場合に備えた保険で,死亡当時の住宅ローンの残債全額が保険金で支払われるものです。
この保険金によって,住宅ローンは完済となりますので,以後,住宅ローンを相続人が支払う必要もありませんし,不動産も,相続人の方が負債のない不動産として相続することができます。
相続人が,保険の存在を知らず,住宅ローンの返済を継続していた場合
住宅ローンを借りた方が死亡した後に,住宅ローンの返済は銀行口座からの引落しがほとんどですので,預金残高があり,銀行に届け出なければ,毎月引落しが実行されます。
上記保険に加入していたことを知らない相続人の方で,銀行に死亡届をせず,そのままにして,住宅ローンの返済が継続していた場合はどうなるのでしょうか?
この場合は,団体信用生命保険契約においては,住宅ローンを借りた方が亡くなった時点で保険金が支払われることになっているので,本来であれば,支払う必要のないものを支払い続けたことになる結果,死亡後に支払ったものの返還を受けることができます。
しかし,住宅ローン債権者は(銀行等)は,相続人から情報を提供しない限り,詳しい状況が分かりませんので,事情を説明する必要があります。
住宅ローンに関する抵当権抹消の手続き
団体信用生命保険金で,住宅ローンの残債がなくなると,次に行うのは,不動産に設定された抵当権の抹消手続きです。
保険金で住宅ローンが完済になっても,金融機関(銀行等)は,自動的に抵当権の抹消手続きを行ってくれることはありません。
まず,住宅ローン債権者から住宅ローンの金銭消費貸借契約書や抵当権設定契約証書など,抵当権を抹消するための書類を送ってくるか,または銀行に受け取りにくるようなご案内があります。
金融機関(銀行等)がやってくれるのはここまでです。
抵当権抹消に必要な書類を受領した相続人の方は,ご自身で管轄法務局に行って抵当権抹消の手続きをするか,あるいは司法書士に抵当権抹消の手続きを依頼することになります(銀行等から受領した書類の中に,このような案内もあります。)。
抵当権の抹消登記には,登録免許税を支払う必要があり,登録免許税の額は,不動産1つあたり1000円となります(土地1筆と建物1棟であれば2000円)。
なお,同一管轄の法務局で20物件を超える場合には,申請1件あたり2万円が上限となります。
銀行等から書類が送られてきたら,できるだけ早い段階で,抵当権抹消の手続きされた方がよろしいかと思います。
たまに見かけますが,銀行から受領した抵当権抹消書類を何年間も放置した結果,書類の紛失や,抵当権者の合併,あるいは,次の相続が発生するなどして,書類を受領した段階で抵当権抹消登記申請をしていれば,比較的簡単に終えることができた手続きが,大変複雑になってきてしまいます。
ここで大きな注意点ですが,上記の抵当権抹消登記申請の前に,相続による不動産の所有権移転登記を行わなければならないということになります。
つまり,当該不動産の所有権を相続人に移転し,その後に,抵当権の抹消登記申請をする,ということになります。
なぜかというと,時系列的に,住宅ローンを借りていた方が死亡し,それにより保険金が支払われて住宅ローンが完済となったため,抵当権を抹消できるのは,不動産を所有した相続人からの申請に基づいて行われるため,その前提として,所有を相続人として所有者の移転手続きを前提として行わなければならないのです。
抵当権抹消登記申請の前に,所有権者を,住宅ローンを借りていた方から相続人に変更しなければ,物権変動の過程を忠実に反映させるというという不動産登記法上の要請にも応えられないため,このような流れになるのです。
似て非なるものとして,相続が発生する前(住宅ローンを借りた方が死亡する前)に,住宅ローンを完済した場合(住宅ローンを組んだ方が繰り上げ返済や約定返済によって完済)には,物件変動の順番としては,住宅ローンの完済の後に死亡と続くため,所有者(権)の移転登記を行うことなく,抵当権の抹消登記申請を,相続人が行えることになります(その後に相続による所有権移転をしても問題なし)。
簡単に区分すると,住宅ローンを完済したとき(抵当権抹消原因が発生したとき)に,住宅ローンを借りた方が生きていたのか,あるいは亡くなっていたのかで区別すると理解しやすいと思います。
団体信用生命保険と相続税
通常の生命保険ですと,保険金が相続人に支払われた場合,みなし相続財産となりますが,団体信用生命保険は,相続人には支払われる性質のものではありません。
したがって,通常の生命保険とは異なり,みなし相続財産には該当しません。
また,相続税で,債務控除というものがありますが,住宅ローンの残債は,相続開始時において確実な債務ということができず,住宅ローンの残債は,死亡と同時に保険金によって完済となるため,これを債務控除することはできません。
以上の結果から,
①団体信用生命保険金は,相続財産に加えない。
②住宅ローンの残債は,債務控除しない(できない)。
③住宅ローンの抵当権が設定された不動産を負債のない不動産として評価する。
ということになります。
それでは,団体信用生命保険に入っていなかった場合はどうでしょう?
相続人の方は,住宅ローンの残債(負債)を法定相続分の割合に従って引き継ぐことになります。
住宅ローンを借りた先(銀行等)には,相続の届出と,今後,誰が住宅ローンを支払っていくのか,所定の書面の提出を依頼されます。
債務も遺産分割の対象とすることができますが,債務については,対債権者の関係もあることから,この債権者(住宅ローン債権者)の同意なく,引き継ぐ債務の割合を相続人間で勝手に遺産分割協議で決めたとしても,相続人間では有効であるものの,住宅ローン債権者に対しては,遺産分割で決めた法定相続分とは異なる割合を対抗することができません。
これは,遺産分割協議によって,資力のない相続人に集中させることも考えられるところ,このような自由があると,債権者に不当な不利益を課してしまうことになるからです。
そのため,銀行等に対し,ある特定の相続人が引き継ぐものと届け出たとしても,その特定の相続人が住宅ローンの支払いをストップするようなことがあれば,他の相続人に対し,相続分に応じて請求していくことになるでしょう。
このような不安定な立場を解消する方法として,免責的債務引受といって,特定の相続人が,他の相続人の債務も全て引継ぎ,引継ぎをした他の相続人は,住宅ローン債務から逃れることができます。
しかし,これは,銀行等の同意が必要でありますし,かつ,特定の相続人(引き継ぐ人)の審査(住宅ローンを借り入れる際に行う審査同様)を行い,その審査をクリアーしてはじめて,他の相続人は相続した住宅ローン債務から離脱できるのです。
または,住宅ローン債務を引き継ぎたくない相続人の方は,相続放棄をすることもできます。
相続放棄の申述が家庭裁判所で受理されれば,住宅ローンの支払い義務は原則なくなりますが,相続登記をして名義人となったり,亡くなられた方の預貯金を取り崩して自己のために費消したりするなどした場合は,単純承認したものとみなされ,相続放棄の申述が受理されない場合もあり得ますので,相続放棄をするかどうか迷ったら,亡くなられた方の遺産には一切関わらない(手を付けない)ことが賢明です。
相続放棄申述が受理されるか
相続人が,被相続人名義の預貯金を解約して,解約した金銭で墓石を購入した行為が,民法921条1号の「相続財産の処分」に当たるか。
≪参照条文≫
第921条
次に掲げる場合には,相続人は,単純承認をしたものとみなす。
1 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは,この限りでない。
以下略
≪判旨≫
被相続人の死後,被相続人名義の預金を解約し,墓石購入費に充てた行為が,民法921条1号の「相続財産の処分」に当たるとして,相続放棄の申述を却下した審判に対する抗告事件において,預貯金等の被相続人の財産が残された場合で,相続債務があることが分からないまま,遺族がこれを利用して仏壇や墓石を購入することは自然な行動であり,また,本件において購入した仏壇及び墓石が社会的にみて不相当に高額のものとも断定できない上,それらの購入費用の不足分を遺族が自己負担としていることなどからすると,「相続財産の処分」に当たるとは断定できないとして,原審判を取り消し,申述を受理した事例(平成14年7月3日大阪高等裁判所決定/平成14年(ラ)第408号)
預貯金債権の相続手続き
【預貯金債権の相続について】(遺産分割の対象になるか)
昨日(平成28年12月19日)の最高裁決定が出るまでの間は,預金債権について,「相続開始(被相続人の死亡)と同時に当然に相続分に応じて分割され,各共同相続人の分割単独債権となる」ことから,遺産分割の手続を要しないものであって,そもそも遺産分割手続の対象とはならないこととされて裁判実務が運用されておりました。
つまり,相続した預金債権については,不動産などと違って遺産分割をするまでもなく,相続開始と同時に,各相続人の相続分に応じて分割承継が既になされる状態になっているのだから,遺産分割の対象とはならない,ということでした。
一方,家庭裁判所で行われる遺産分割調停等においては,預金債権も遺産分割の対象とする合意があれば,遺産分割の対象とする例外運用はなされていました。
もっとも,相続開始と同時に相続分に応じて分割されるからといって,共同相続の場合において,銀行の窓口に行って「私の相続分だけを払い戻してほしい」と言っても,相続人全員の印鑑証明書を持ってきてほしいなど,法律上は直ちに分割されているとはいえ,銀行実務では,二重払いの危険などの理由からこの運用はされてきませんでした。
なお,それに納得できない相続人は,自己の相続分について,預金払い戻しに関する訴訟を提起すれば,裁判所は,当然分割承継説ですので,勝訴判決が出ていたものです。
昨日の最高裁決定の原審(大阪高裁)も「本件預貯金は,相続開始と同時に当然に相続人が相続分に応じて分割取得し,相続人全員の合意がない限り遺産分割の対象とならない」などとしたものの,最高裁は,それを次のような理由から,原審の決定を破棄して,事件を大阪高裁に差し戻したものです。
不動産の相続登記手続きについて
不動産の相続登記手続きについて
不動産を所有している方が,不幸にしてお亡くなりになった場合,避けて通れないのが,不動産の相続登記手続きです。
不動産の相続登記手続きは,いつまでにしなければならない,という期限は法律上設けられておりませんが,年数の経過により,相続人の方がさらにお亡くなりになり,二次相続が開始することもあります。
当初,相続人が3名であったものが,放置していたことにより,5名,6名・・・と相続人が増えていくことも珍しいことではありません。
関係者が増えていくということは,その分,集める書類も多くなりますし,遺産分割協議をする場合においても関係者全員で調整を図らなければなりません。
相続登記手続きを行う際に,必要なことをまとめてみます。
嫡出子と非嫡出子の相続分
嫡出子と嫡出でない子(非嫡出子)の相続分は,従来,平等ではなく,非嫡出子は,嫡出子の2分の1と定められていました。
嫡出子とは,法律上の婚姻関係にある男女間に生まれた子で,非嫡出子とは,法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子をいいます。
子の父親(婚姻関係にない子を法律上子と認められるためには認知が必要)は,婚姻していようとしていまいと自分の子に変わりはなく,また,子の母親は,出産の事実から婚姻していなくても母親になりますので,両親が,婚姻関係にあろうとなかろうと,子には何も責任がないにもかかわらず,この不平等な取り扱いは,平成25年9月4日の最高裁の決定が出るまで変わることはありませんでした。
この最高裁決定では,憲法第14条に規定する法の下の平等に反するとして,嫡出子・非嫡出子の相続分は平等であるとしたのです。
これにより,民法第900条4号ただし書き中「嫡出子でない子の相続分は,嫡出子である子の相続分の2分の1とし」という部分が削除されることになりました(平成25年12月11日施行)。
これを受けて,法務省民事局長の通達(民法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記等の事務の取扱いついて)が発せられることとなりました。
同通達において,「第1 改正法の概要」の中で,
①嫡出子も非嫡出子も,相続分は同等とする。
②施行期日は,公布の日(平成25年12月11日)から施行する。
③改正法は,平成25年9月5日以降に開始した相続について適用し,同月4日以前に開始した相続については,何ら規定するものではない。
次に,同通達「第2 不動産登記等の事務の取扱い」として,
①平成25年9月5日以降に開始した相続については,新民法(相続分平等)を適用する。
②平成25年9月4日以前に開始した相続について,最高裁決定は,「本件規定(旧民法900条4項)は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである」と判示しつつ,旧法の不平等な規定を前提としてなされた「遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない」とされた。
③平成25年12月11日以降にされる不動産登記等の申請であって,平成13年7月1日以降に開始した相続における法定相続(遺言や遺産分割等によることなく,被相続人の法定相続人となったこと自体に基づき,法定相続に応じて不動産等を相続したこと)に基づいて,権利を取得した者を登記名義人とする登記を申請する際は,嫡出子も非嫡出子も同等であるものとして事務処理をする。
④平成25年12月11日以降に申請で,平成13年7月1日以降に開始した相続で遺言や遺産分割等に基づいて登記をする場合には,当該遺言や遺産分割等の内容に従って事務処理をすれば足りる。
⑤平成25年12月11日以降にされる申請で,平成13年7月1日以降に開始した相続における法定相続に基づいて権利を取得した者の登記に係る更正の登記を上記③④以外の申請等については,当該登記の原因に応じて,最高裁の判示する「本件規定の前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係」に基づくものであるかどうか等を判断して事務処理をする。
この通達により,平成25年9月5日以降に発生した相続については,嫡出子も非嫡出子も相続分は平等であるとして事務処理をする,ということになり,平成25年9月4日以前に開始した相続については,
平成25年12月11日以降にした不動産登記等の申請で,相続の開始が平成13年7月1日以降のものについて法定相続により登記をする場合は,嫡出子・非嫡出子の相続分は同等として事務処理をする。
ただし,法定相続ではなく,遺言や遺産分割協議等に基づく登記等の申請については,その遺言や遺産分割協議の内容に従って処理すればよい。
また,平成13年7月1日以降に開始した相続で,法定相続により登記をしたものの,その更正などの登記をするときは,確定的なものとなった法律関係は覆らないことを勘案して事務処理をする,としております。
相続の開始した日によって取り扱いが異なってきますので,注意が必要です。
千葉県民司法書士事務所のオフィシャルサイト http://chiba-shihoshoshi.com/
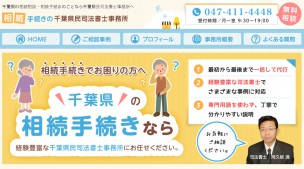
最近のコメント