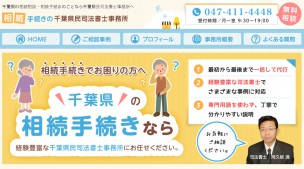住宅ローンがある場合の債務整理
住宅ローンの残額がある方が亡くなってしまった場合で,相続放棄もせず期間が経過しまった場合,住宅ローン債務や,その他のお亡くなりになった方の借金も相続する(引き継ぐ)ことになります。
その場合,相続人が住んでいる不動産であれば,それを手放したくないお気持ちは十分に理解できるところです。
また,相続人自身にも債務があった場合,自身の債務と合わせて被相続人の債務も返済していかなければならず,大きな負担になります。
もっとも,支払いが難なく実行できるのであれば,約定のまま支払いを継続していけば問題はないのですが,支払いが厳しい場合には,返済を楽にする方法を検討する必要があります。
一般的な債務整理の方法についてご説明します。
主に,住宅ローン及び住宅ローン以外の借金も相続してしまったり,相続した債務に合わせて相続人自身にも借金がある場合を想定しています。
任意整理をする場合
住宅ローンがあっても,任意整理は可能です。
住宅ローンは,任意整理の対象にはなりませんが,住宅ローン以外の借金を任意整理することによって債務を圧縮して,住宅ローンの返済を少し楽にすることができます。
また,住宅ローン以外の借金を圧縮しても,それだけでは,住宅ローンの返済が楽にならない場合には,住宅ローンの返済自体を軽くすることも考えなければなりません。
住宅ローンについて,利息ゼロにすることはできませんが,返済期間を延長したり,元金据置といって,住宅ローン以外の債務について,任意整理で決まった期間の返済が終わるまでの間は,元金だけ支払って,住宅ローンの利息は,任意整理の期間が満了した後に上乗せして支払うというものです。
しかし,これには,住宅ローン債権者の承諾が必要となるため,簡単にはいかないことも多くあります。
借り換え(A銀行の住宅ローンを,B銀行で新たに住宅ローンを組んで完済して,利率などの好条件の住宅ローンに切り替えるというもの)も検討することになりますが,住宅ローン以外の負債は,信用情報機関に登録されているため,住宅ローンの申し込みをしても,審査に通りにくいことが想定されます。
このような場合には,住宅ローンは現状のまま支払いを継続していくこととし,住宅ローン以外の借金について月額返済額を大きく減らす必要があります。
まずは,住宅ローン以外の借金について,どの程度まで毎月の返済額を減額させることに成功するのかが一つの鍵となります。
なお,住宅ローン以外の借金に関しては,任意整理をすると,それ以降の利息の支払いは原則免除になりますので,返済計画が立てやすくなります。
今までは,毎月1万円を返済しても,7000円は元金に充当されますが,残りの3000円は利息の返済に充てられるため,元金は7000円しか減りませんが,任意整理を行うことで,毎月1万円を支払えば,確実に元金が1万円減っていくことになります。
注意点としては,住宅ローン契約の約定に,次のような定めがあった場合です。
第〇条 お客様が,次の各号の一つにでも該当する事由が発生した場合は,当社からの通知,催告等がなくても,本契約による一切の債務につき当然に期限の利益を失い,直ちに債務を全額返済するものとします。
①お客様に破産,民事再生の申立てがあったとき
②お客様の預金その他の当社に対する債権について,仮差押または差押命令,通知が発送されたとき
(以下略。なお,銀行毎に文言や内容が異なりますので,ご自身の住宅ローン契約書等でご確認ください。)
住宅ローン以外の借金について,その債権者から住宅ローンを組んだ銀行に対する預金が差押を受けた場合,上記条項では,そのときにある住宅ローン残債を全額一括で返済(以後,分割返済はできないということ)しなければならなくなりますので,住宅ローン以外の借金については,遅滞に陥る前に適切に対処する必要があります。
個人民事再生の場合
民事再生は,該当する当事務所のオフィシャルホームページの該当ページをご参照いただきたいのですが,概要を述べると,住宅ローン以外の借金が,大幅に減額され,その減額された金額を原則3年で返済していくものとなります。
仮に,住宅ローン以外で500万円の借金があった場合,裁判所から再生計画の認可決定をもらうと,この500万円という借金が100万円に減額され,この減額された100万円を原則3年間で支払い,無事に支払い終えれば,500万円あった債務がゼロになるという手続きです。
この例ですと,月額返済額は,約2万7778円となり,500万円の借金を支払っていたときに比べれば,大きな減額になり,住宅ローンの返済がより支払いやすくなります。
しかし,任意整理と違って,個人民事再生の場合は,裁判手続きとなりますので,上記一例でありますが住宅ローン契約の約定にもあるとおり,民事再生の申立てをすると全額一括返済という事態にもなりかねませんが,個人民事再生には,住宅ローンに関し,特別な規定(住宅ローン特別条項)があり,これを利用できる限りにおいては,一括返済を強いられることはありませんのでご安心ください。
また,個人民事再生の申立をする際には,事前に,住宅ローン債権者との事前協議というものが必須となります。
したがって,住宅ローン特別条項を使う個人民事再生の場合には,住宅ローン債権者に内緒で手続きを進めることはできませんし,逆にいうと内緒にする必要もないのです。
なお,既に住宅ローンの返済に遅れが生じている場合で,保証会社への代位弁済が実行されてから6か月が経過してしまうと,住宅資金特別条項は使えなくなるので注意が必要です。
住宅ローンの支払いが滞ってしまう前に,まずは,無料相談をご利用いただくことをお勧めします。
自己破産の場合
この場合は,自宅の確保は,困難になります。
もし,この家にどうしても住み続けたいという強いお気持ちがあれば,親族に自宅を購入してもらって賃貸借等で済むか,あるいは自分たちが住み続けることを条件として購入してくれる買主を探さなければなりません。
買手が親族の場合には,賃料については柔軟に対応してくれると思われますが,第三者の場合には,投資として購入しているため,相場の賃料をそこに住んでいる間支払い続けなければなりません。
支払いを滞れば,明け渡しの請求を受けて,結局は,そこを出ていかなければならなくなります。
もしかすると,住宅ローンを支払っていたときとあまり変わりない金額の賃料になるかもしれませんし,これでは,何のために破産をしたのか分からなくなる場合もあります(このような場合には,上記の個人民事再生を先に検討してもよいでしょう。)。
この辺は,住宅ローン以外の借金先や借金の額にもよって異なってきますが,十分な検討が必要です。
自宅確保を諦めて自己破産をする場合
選択肢としては,大きく分けると2つあります。
1 住宅ローン債権者(または保証会社)が競売の申立てを行い,第三者に落札されるまで,その自宅に住み続ける。
この場合,住宅ローンの滞納状況や物件の評価によっても異なってきますが,半年間程度は住み続けられます(落札者が現れなければ,もう少し長く住んでいられます。)。
この間に,転居先を探したりするなどして出ていく準備をしていくことになりますが,この期間は,執行裁判所の進み具合や物件の立地などによっても異なるため,不確定要素が多くあり,いつでも出ていけるように準備をしなければなりません。
2 自宅を任意売却する。
競売という裁判所が関与する強制的な手放し方ではなく,簡単にいうと,自宅(不動産)を売主として条件の合う第三者に売却することになります。
任意売却のメリットとしては,
予め引越しなどの日程を,自分たちで柔軟に決めることができる。
一般的に,競売よりも高値で取引されるため,保証人などがいる場合,債務をより圧縮することができる。
形式的には,通常の売買なので,近所の方に住宅ローン等の滞納があることなどを知られる心配が減少する。
引越費用を,一定程度は確保できる(場合によっては持ち出しなく引越しができる。)。
滞納しているマンション管理費等がある場合,任意売却で清算される。
住宅ローン債権者も,競売よりも高値で売れるということは,それだけ多く回収できるので,協力的である。
任意売却後の住宅ローンの残額について,事情に応じて低額な金額での分割弁済の合意ができる可能性があり,合意した内容を履行している限りにおいては,給与等の差押えは原則ない。
競売の最大のメリットは,
何も自分たちでする必要がない(法律の規定に従って淡々と進められる。)。
一方任意売却のデメリットとしては,
抵当権が複数ある場合,後順位抵当権者が同意しないと成功しない。
自分で交渉することは困難なため,不動産業者に依頼しなければならないが,専門の不動産業者であれば,持ち出しゼロで,仲介手数料は,最後に売買代金から清算するが,専門でない不動産業者の場合,費用を請求されたりするケースもある。
既に競売手続きが開始している場合,時間的制約があり,期限内に買主が見つからない場合には,競売が先に完了してしまう可能性がある。
形式的には,通常の売買ですので,購入希望者に内覧させ,その立会も場合によってはしなくてはならない。
競売のデメリットは,
裁判所から選任された評価人や執行官が,自宅周辺で写真を撮影したりして近所の目が気になる。
競売物件は,裁判所で内容を閲覧したり,インターネットで公告されるため,一般的に近所の方が知ることは少ないと考えられるが,情報が公開されることにより,購入希望者や競売専門業者等が,近所に聞き込みをすることあるため,近所に不審に思われる可能性がある。
なお,参考までに民事執行法上,現地調査として次の規定がある。
民事執行法第57条
- 執行裁判所は,執行官に対し,不動産の形状,占有関係その他の現況について調査を命じなければならない。
- 執行官は,前項の調査をするに際し,不動産に立ち入り,又は債務者若しくはその不動産を占有する第三者に対し,質問をし,若しくは文書の提示を求めることができる。
- 執行官は,前項の規定により不動産に立ち入る場合において,必要があるときは、閉鎖した戸を開くため必要な処分をすることができる。
- 執行官は,第1項の調査のため必要がある場合には,市町村(特別区の存する区域にあつては、都)に対し,不動産(不動産が土地である場合にはその上にある建物を,不動産が建物である場合にはその敷地を含む。)に対して課される固定資産税に関して保有する図面その他の資料の写しの交付を請求することができる。
- 執行官は,前項に規定する場合には,電気,ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を行う公益事業を営む法人に対し,必要な事項の報告を求めることができる。
このような事態にもなりかねません。
いえることは,返済ができないと思ったら,迷わず,専門家に相談をすることが重要です。
返済が滞り,債権者からの督促が厳しくなってから相談に訪れる方は後を絶ちません。
もう少し早く相談してくれれば・・・間違った相談場所でアドバイスを受けなければ・・・
そうなる前に,その道に詳しい専門家に出会えることが,債務整理が成功するか否かの鍵になるのかもしれません。